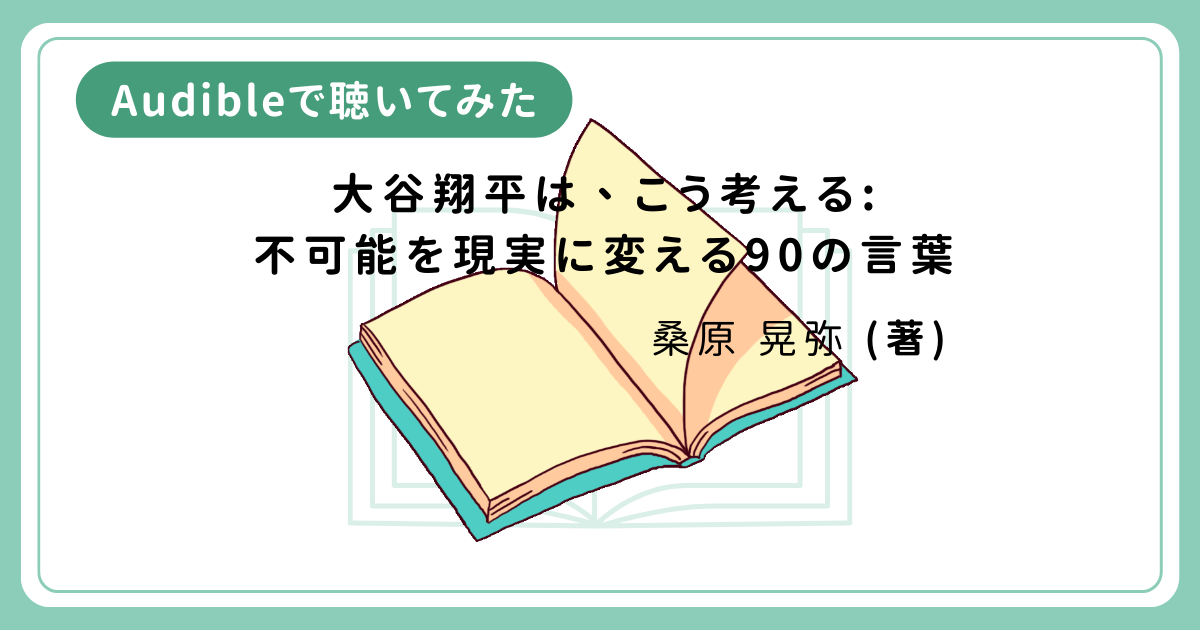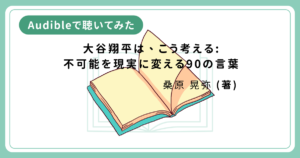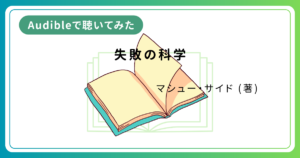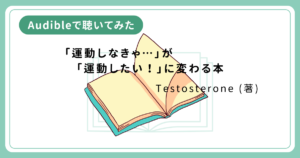2025年3月15日、大谷翔平選手がロサンゼルス・ドジャースの一員として東京ドームに登場し、読売ジャイアンツとのプレシーズンゲームに「1番・指名打者」で出場しました。日本でのプレーはWBC準々決勝以来、約2年ぶり。第2打席では豪快な2ランホームランを放ち、ファンを魅了しました。試合後には「久々に帰ってきた感じがした」と語り、その言葉に感動した方も多かったのではないでしょうか。
彼の活躍の背景には、明確な目標設定、挑戦への意欲、継続の力があります。その考え方は、スポーツの枠を超えて、働き方改革を進める企業の課題解決にも活かせるものです。
今回は、書籍『大谷翔平は、こう考える』をもとに、職場づくりや人材育成に役立つ3つの視点を、社会保険労務士の立場からご紹介します。
明確な「目標設定」こそが、働き方改革の土台になる
マンダラチャートに学ぶ、目標と行動の具体化の手法
大谷翔平選手が高校時代から使っていた「マンダラチャート」は、中央に目標を書き、その周囲に達成のための要素を展開していくフレームワークです。最終的に、具体的な行動レベルまで落とし込むことで、目標と行動が直結する仕組みが可視化されます。
これは、企業が進める働き方改革の推進にも非常に有効です。
- 「働き方改革を進めたいが、何から手を付けるべきか分からない」
- 「掲げた目標が、社員の行動に繋がっていない」
こうしたお悩みを抱える企業様にこそ、この考え方はヒントになります。「働き方改革の目標」を設定し、その達成に必要な要素(業務改善、人材育成、制度改革など)を整理していく。そして、そこから具体的なアクションプランを描く――まさにマンダラチャート的な視点が、改革を机上の空論にせず、現場で機能させる鍵となります。
挑戦を後押しする風土が、組織をしなやかにする
社員の「やってみたい」をどう支えるか
大谷選手は、誰も歩んだことのない「二刀流」という道を、自らの意思で切り拓いてきました。その姿勢は、ビジネスの現場でも見習うべき点が多くあります。
職場でも、「新しいことに挑戦したい」と考えている社員が必ずいます。しかし、それを後押しできる環境が整っていなければ、その意欲は埋もれてしまいます。
- ミスが許容される文化があるか?
- 新しい挑戦を評価する仕組みがあるか?
柔軟な働き方や新制度への取り組みも、挑戦を後押しする文化があってこそ成功します。挑戦できる職場は、人材が成長し、組織が時代に強くなる基盤です。
継続を支える仕組みが、働き方の質を変える
意識ではなく、仕組みで続ける
大谷翔平選手の高いパフォーマンスは、「継続」から生まれています。日々の練習、生活管理、自己研鑽――それを可能にしているのは、継続を支える明確なルールや習慣です。
職場でも、「継続できる仕組み」が整っているかは重要です。
- 定期的な業務改善の機会(PDCA)が確保されているか?
- 健康経営や働き方改革の施策が、形だけで終わっていないか?
「頑張ろう」では継続は難しく、制度・評価・環境整備といった仕組みの後押しがあってこそ、持続可能な働き方改革が実現します。
まとめ:名言から「気づき」、そして「変化」へ ~小さな行動が職場を変える~
大谷翔平選手の名言には、仕事に活かせる考え方が凝縮されています。
目標設定の工夫、挑戦を支える文化、継続を助ける仕組み――それらはすべて、働き方改革を「実行」するための大切な視点です。
社労士として、これまで多くの職場を見てきた中で、「少しの工夫」で組織が大きく変わる事例を数多く見てきました。
貴社の現場でも、「どこかに活かせそうだな」と思える視点がありましたら、ぜひ一度、社内での話題にしてみてください。もし「自社で応用するならどうすれば?」というご相談があれば、私たち社労士もお力になれるかもしれません。
小さな気づきから始める変化を、ぜひ一緒に考えてみましょう。
そして、行動のきっかけとして、今回ご紹介した書籍をぜひ手に取ってみてください。
手元に置いて、何度でも読み返したい方に。
大谷翔平の名言をじっくり味わいたい方におすすめです。
\ 大谷翔平の言葉を「読む」も「聴く」も選べる /
※上記リンクはアフィリエイトを利用しています。